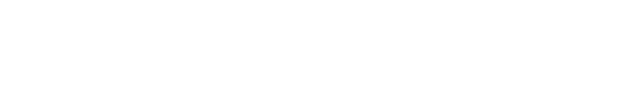甲状腺細胞診における液状化検体細胞診
はじめに>
液状化検体細胞診(liquid-based cytology;LBC)とは、採取した細胞を固定保存液に回収後、専用の医療機器を用いて細胞診検査用標本を作成する技術です。
甲状腺細胞診へのLBC導入のメリット
・標本作成の標準化
・検体不適正率(unsatisfactory rate)の減少
・LBC標本独自の細胞所見や免疫細胞化学染色による診断精度の向上
・鏡検作業の負担軽減
当院では2025年からLBC(BD, CytoRichTM法 日本臨床に依頼)を導入しており、文献を参考に、LBC標本作製法、細胞所見、導入意義、適応について述べる。
LBC標本作製法
|
細胞沈下法 |
フィルター転写法 |
|
|
原理 |
遠心で得た沈査を浮遊させ、重力による自然沈下でスライドに接着させる。 |
細胞を分散させ、フィルターに吸引し、スライドに圧着転写させる。 |
|
主な製品名 |
CytoRichTM(BD) |
ThinPrep® (Hologic) |
|
自動塗抹法 |
◯ |
◯ |
|
塗抹範囲(直径 mm) |
13 |
13か20 |
|
細胞像 |
立体的 |
平面的 |
LBC標本作成法は、フィルター転写法と細胞沈下法の2つに大別される(上記)。
当院では日本臨床の検査課にどちらが良いかを聞いて、CytoRichTM法で検査依頼している。ThinPrep®法はフィルターを用いるため、スライドガラスに大きな細胞集塊が載らなかったり、細胞核の染色が薄い傾向があるそうです。一方、CytoRichTM法はLBC溶液中の細胞を最大限集める事が可能で、papanicolaou染色での染色性が良く、組織構築を反映した立体的な細胞像が得られるということでこちらを選択した。
検体採取
穿刺針を専用の固定液であるCytoRich TMRED保存液(CR-R)にて洗浄したものを検体とする。
固定液
CytoRich TM保存液には赤色と水色(CR-B)のものがある。CR-Rは少量のホルムアルデヒドが含まれており、蛋白可溶化作用や溶血作用があるため、蛋白成分と赤血球が概ね除去されており、背景はクリアである。甲状腺細胞診では、血性検体が多いことから、蛋白可溶化作用や溶血作用がある保存液が望ましい。
細胞所見
|
CytoRich TMRED保存液 を用いたLBC標本の細胞学的特徴 |
|
背景成分(赤血球やコロイドなど)の減少 |
|
重なりは少ないが、立体的な塗抹 |
|
孤立散在性細胞の減少 |
|
核密度やN/C比の増加 |
|
細胞の収縮、小型化 |
|
細胞質、核の濃染傾向 |
|
核小体の好酸性、明瞭化 |
|
乳頭癌:高細胞型を認識しやすい、核の重畳、スリガラス状クロマチンは観察困難、ジグザグ核は観察可。 |
|
髄様癌:有尾状細胞質を認識しやすい。 リンパ腫:核の膨化、変性クロマチン |
良い点:
固定液に溶血作用、蛋白可溶化作用があるため、赤血球やコロイドなどの背景成分が減少する。但し、粘稠なコロイドや泡沫細胞、変性赤血球は減少しにくい。
また、細胞沈下法では細胞集塊や大型細胞が優先的に塗沫されるため、通常塗沫標本で嚢胞液のみ塗沫されているケースでも、LBC標本では、上皮成分が塗沫されている可能性があり、良悪を判定できることがしばしばある。
採取された細胞は、塗沫される前に固定されることから、細胞変性が少なく、細胞形が保持されやすい。したがって、高細胞型乳頭癌における高円柱状細胞や髄様癌細胞の有尾状細胞質を容易に認識できる。脳回状の凸凹不整が核縁の半周以上に認められるジグザグ核(convolted nuclei)はLBC標本の乳頭癌細胞のみを認められる。重要な診断的特徴である。
一方、細胞は収縮、小型化するため、細胞質や核が濃染傾向を示し、乳頭癌に特徴的な角の重畳やガラス状クロマチンの観察は困難になる。
LBCにおいて、リンパ腫細胞は減少するため、診断に一見不向きのようにみえるが、LBC標本では慢性甲状腺炎にはみとめられないような核の膨化とクロマチンの変性が出現することに注目すると良い。
LBC標本を観察する場合、このような特徴を理解するべきであり、正確に判定するにはある程度の経験が必要とされる。
LBC導入の意義
- 効率的な細胞回収と、標準化された細胞操作による検体不適正率の減少である。多くの施設からLBC導入により不適正率が半減することが報告されている。
甲状腺癌取り扱い規約第8版には、検体不適正率が、細胞診検査総数の10%以下が望ましく、10%を超える場合は採取方法、標本作製法についての検討を要すると記載されている。
- 通常塗抹標本では、採取細胞量のみならず、塗抹固定の技術も標本の不適正率に影響を及ぼすが、LBC標本では影響を受けず、塗抹操作による変性のない標準化された標本が可能である。通常と塗抹標本と塗抹標本作成後の針洗浄液を用いたLBC標本を併用し、両者の細胞像を比較する期間を設けることが推奨されている。
- 免疫細胞化学染色に適していることが挙げられる。1つの検体から複数枚の標本を作製できる、背景がクリーンで、共染が起こらない、細胞質の保持能力が高いため、細胞質染色が良好な点等がその理由である。
- 塗抹範囲が直径13〜21mmと小さく、細胞の重なりが少ないので、鏡検の負担軽減につながることである。
デメリット>
標本作成が煩雑でコストがかかることが挙げられる。ただし、2012年度より通常塗抹標本で再検が必要と判断された場合のみ、液状化検体細胞診加算として85点の保険請求が認められるようになった。
通知では「液状化検体細胞診加算は,採取と同時に作製された標本に基づいた診断の結果,再検が必要と判断され,固定保存液に回収した検体から再度標本を作製し,診断を行った場合に限り算定できる。採取と同時に行った場合は算定できない。」と規定されている。よって、以前に採取済の検体で再検査する場合が該当する。
LBCの適応>
LBC標本作成にはコストがかかるため、LBCが効果的だと思われる症例のみ、固定液で針洗浄している。といっても、現場ではプレパラートに吹き出し検体の様子を見て判断することになるだろう。
具体例が文献で挙げられている。
- 採取細胞量が少ない。
- 血液が多い。
- 嚢胞液
- 固定時に乾燥させてしまった。
- 免疫化学染色が有用な疾患(髄様癌や篩型乳頭癌など)の可能性がある場合
参考文献>鈴木彩奈,他,内分泌外会誌 37 (1)39-43,2020