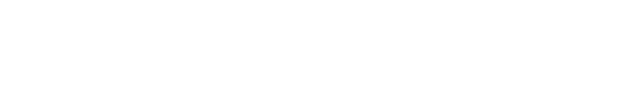25.08.03 合併症 ー甲状腺穿刺吸引細胞診ー
-
疼痛・不快感
・最も頻度が高い合併症で選手を受けた患者のことと見られる。
・極めて激しい疼痛、上腕に及び激痛訴えた場合は、神経鞘腫を疑い、穿刺を中止する。ただ、神経鞘腫の全例に見られるわけではない。
・疼痛が強い場合は、局所を保冷剤で冷却する。
-
出血
・顕微鏡的な出血まで考慮すれば、ほぼ全例に出血があると考えられる。
・出血部位は、①結節内、②甲状腺と前頸筋の間の結合組織、③皮下の順に多い。
・抗凝固薬、抗血小板薬、内服中や血液、透析患者では出血が起こりやすいと思われるが、内服の中止はせず、穿刺後の圧迫時間を長くする。(当院では中止している)
-
血管迷走神経反射
・血管迷走神経反射は0.45〜1.28%の頻度で報告されている。
・穿刺後に見られる徐脈や失神は一過性で頭を低くし、下肢を上げると通常は2〜3分間で回復する。
-
感染
・甲状腺は血流が豊富で要素が含まれていることから、もともと感染しにくい臓器であり、感染を合併する事はほとんどない。
・嚢胞性結節、免疫不全、患者、アトピー性、皮膚炎等が細菌性感染症のリスクである。
-
反回神経麻痺
・麻痺は片側性である。嗄声は一過性で穿刺した翌日〜2日目に発症し、2〜6ヶ月までには自然回復する。
・主な原因は、穿刺針による神経の直接障害ではなく、穿刺による血腫や炎症が神経の圧迫や伸展を引き起こすことである。
・反回神経は左右で走行が異なるため、その位置をよく理解した上で穿刺する。
-
急性一過性甲状腺腫大
・穿刺後、数分以内に発症し、腫大は最大4.5倍にも及び、ぞっとする位急に腫れるため、“Thyroid thriller”と呼ばれている。
・特徴的な超音波所見がみられる。甲状腺は両側性、時に片側性に腫大し、血流のない樹枝状の低エコー(hypoechoic crack)が観察される。
・結節部の腫大や甲状腺周囲の出血は伴わない。
・甲状腺腫大は一過性で、1〜20時間程度で軽快する。呼吸困難をさせないため、局所の冷却のみで経過観察可能であるが、挿管にまで至った症例報告もあると。
・ステロイドの点滴の効果は定かではない。
-
気管穿刺
・気管前にある結節を穿刺する際、空気の吸引や血痰を伴う外傷の出現で、気管穿刺を知ることができる。
・気管前にある結節を穿刺する場合、交叉法ではプローブで結節を側方から圧迫し、反対側に結節を移動させて、穿刺すれば、気管穿刺を防ぐことができる。
-
穿刺経路再発
・がん細胞が穿刺経路に沿って広がり、再発することがある。頻度は穿刺5年後で0.15%、10年後で0.37%と報告されている。
・病変は、皮膚、皮下脂肪、組織、筋肉、甲状腺内などに多発する傾向にある。
廣川満良、他., 超音波・細胞・組織から見た甲状腺疾患診断アトラス(第一版) 17-33, 2022 を参考に、一部改、追記