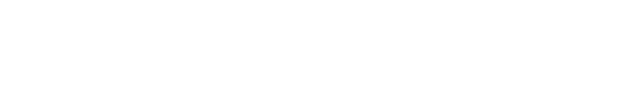25.07.21 甲状腺穿刺吸引細胞診
目的と適応
甲状腺結節の術前診断として最も信頼性があり、多くの症例で腫瘍の組織型を推定できるが、最も重要な目的は良性と診断することによる不必要な手術の回避である。
・甲状腺機能亢進状態のバセドウ病患者、頸部を静止できない患者、インフォームド・コンセントが得られない患者では行えない。
・出血傾向や抗凝固薬服用中の患者は一般的に禁忌とはしない。
・明らかな良性病変(亜急性甲状腺炎、慢性甲状腺炎、良性嚢胞など)、5mm以下の結節(ATAでは1.0cm以下)、機能性結節などは適応外。
・リンパ節では、悪性が疑われる、あるいは悪性の可能性がある超音波所見(嚢胞化、微小石灰化、血流増加、高エコー結節、リンパ門消失、円形化)が見られる場合に行う。
(上記を参考に、筆者作成)
穿刺法
・高い診断精度を得るためには、的確に病変部を穿刺し、適切に塗抹することが重要である。
・穿刺法や塗抹法は臓器、病変、穿刺物の性状や量により、適宜最適な方法を選択することが重要である。
前処置
・前処置として特別な事はなく、通常局所麻酔は行わない。小児の場合には鎮静剤を投与することもある。欧米では局所麻酔や痛み止めの湿布を貼る施設もある。
・抗凝固薬、抗血小板剤の服用は絶対的禁忌ではない。当院では、通常の休薬期間で対応している。服薬を中止する必要がないと言う方針でされている病院もある。
・最も重要なのは安全に穿刺することであり、穿刺針を刺入している数秒間は、以下を患者に理解してもらい協力を求める。患者の緊張と不安を極力軽減させる配慮も重要である。
- 動かない。
- 声を出さない。
- 嚥下しない。
穿刺方法
ピストル型ホルダー法:当院では、ピストル型ホルダーに注射器を装着する方法を採用している。
以前、千葉大学方式のピストル型ホルダーがあったが、今は製造中止で再開の見込みはないそうでる。当院ではSwedenの医療機器会社に問い合わせ、輸入したものを用いている。
刺入法:交叉法について
利点:・穿刺針が短く、最短距離(多くは2cm以内)で到達する。・針先の自由度が高い。・穿刺針の剛性が強く、石灰化結節に適する。・目的部位に到達しやすい。・周囲臓器損傷の危険性が低い。・検査時間が短い、などがある。
欠点:・針先しか描出できないので、目標物に届かない、通り抜けてしまうこともありうる。
患者の体勢
・患者の前頚部をできる限り進展させることが重要。椅子の際は天井を見上げるようにヘッドレストを調整する。以下の利点がある。
・甲状腺が動きにくくなり、結節が固定されやすい。
・皮膚から結節までの距離が短くなる。
・下極側に位置する結節が上方に移動し、穿刺しやすくなる。
・頚部前の空間が広がり、穿刺操作しやすい。
穿刺部位の見極め
・不均質な充実性結節:低エコー部を穿刺する。低エコー部は腫瘍細胞が密集している部位である。
等エコーや高エコー部は、線維化、壊死、出血、石灰化を含む非診断領域である。
・充実部と嚢胞部が混在する結節:充実部を穿刺する。
・結節内結節(nodule in nodule)、突出性結節(nodule from nodule):それぞれの部位を穿刺する。
・衛星結節を伴う結節:主結節と衛星結節の両方を穿刺する。ともに濾胞性腫瘍で類似した細胞像であると、画像所見を加味し濾胞癌を推定できる。
・石灰化結節:石灰化型節内への侵入を試みる。細い針、長い針はなるため不向きである。
・リンパ腫の疑い:結節の中央もしくは最も低エコーの部を穿刺する。辺縁部では橋本病との区別が難しい。
・未分化癌の疑い:結節の周辺か、ドプラで血流のある部を穿刺する。結節の中央は、しばしば壊死に陥っているため、正確な診断ができない。
・びまん性硬化型乳頭癌の疑い:結節部がないため、砂粒体の密度が高い部分を穿刺する。密度が高い部分を穿刺する。境界が不明瞭な結節様病変があれば、そこをターゲットとするが、本亜型
に特徴的な細胞所見は、この部からは得られない。
穿刺手順
- 固定する:目的とする結節が動かないように固定することが重要。患者には出来る限り前頚部の皮膚を進展してもらい、プローベで適宜、強く圧迫する。これにより結節内の血流が減少し、内圧が上昇。細胞が採取しやすくなるという理論である。交叉法では、プローベで結節を斜め下から強めに圧迫し、針を皮膚に対して垂直に刺入できるようにする。
- 刺入する:穿刺針を結節内に差し込み、エコーで針先が結節内にあることを必ず確認する。ゆっくり刺入(慌てず、位置がずれていたら針を後退させ、向きを調整し、また進む)すると、針先を確認しやすい。
- 陰圧をかける:針先、結節内に到達したら、わずかに陰圧をかけた状態で切り取り操作を行う。陰圧の程度は3mL以下で充分であり、陰圧をかけなくても細胞は採取できるそうである。
- 切り取り:細胞を採取するのに最も重要。陰圧によるのではなく、針先での切り取り操作により組織を採取すると理解する。陰圧状態のまま針を前後に素早く(1秒間に3回程度)動かす。(ピストン操作)か、針先を回転させる。ピストン操作が早ければ早いほど採取細胞量が多くなる。ピストン操作の際に針の方向を変える事は出血を引き起こすからダメ。針先が結節外に出ないように注意する!切り取り時間は3秒以内に留める。切り取り時間を長くしても細胞ではなく、血液を吸引するだけであり、検体不適正率は減少しない。採取する検体量は、針内の容量で充分である。嚢胞液の場合は、十分に陰圧をかけ、シリンジ内にまで吸引する。
- 抜去する:針を抜去する前に必ず陰圧を解除する。陰圧状態のまま抜去すると、採取した材料がシリンジ内に移動して乾燥変性を起こす上に排出しにくくなる。
- 排出する:穿刺針をシリンジから外し、シリンジに空気を入れてから、再び穿刺針を装着し、検体をスライドガラス上に1回で吹き出す(針先をスライドガラスに向けること。周りに飛び散らせない)。その後、LBC検体に回すことがある。
圧迫
穿刺後、侵入部を清潔なガーゼや絆創膏を上から圧迫する。穿刺後の出血は通常数分の圧迫で抑えることができる。隈病院では、15分間圧迫している。抗凝固薬を服用している場合は20分間圧迫し止血確認を行う。
廣川満良、他., 超音波・細胞・組織から見た甲状腺疾患診断アトラス(第一版) 17-33, 2022 を参考に、一部改、追記