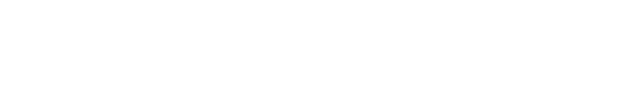バセドウ病の薬物治療
バセドウ病の薬物治療
未治療患者では、原則としてすべての患者に適応となる。
-
第一選択薬:チアマゾール(MMI)
妊娠初期(器官形成期の妊娠4週0日〜15週6日)を除き、MMIを選択する。無機ヨウ素単独での治療は甲状腺クリーゼやバセドウ病術前、131I内用療法前後で甲状腺機能をコントロールする場合に行い、一部の軽症例等では抗甲状腺薬に変わる内服治療薬として使用可能である。ヨウ素制限は行いことが弱く推奨した。炭酸リチウムは海外では有用性が報告されているが、我が国では保険適応がない。
MMIは、PTUよりも早く甲状腺ホルモンが正常化でき、副作用の発現頻度が低く、1回/日投与で良い。
推奨されるレシピ>
軽症〜中等症(FT4 5ng/dL未満):メルカゾール(5mg)3錠分1朝後
重症 (FT4 5ng/dL以上):メルカゾール(5mg)3錠分1朝後+KI50mg(ヨウ素として38.2mg)の併用
しかし、メルカゾールの添付文書には、ガイドラインの方針が反映されておらず、
「通常成人に対しては、初期量1日30ミリグラムを3回から4回に分割経口投与する。症状が重症の時は、1日40から60ミリグラムを使用する。」とされているので注意する。
現在、日本甲状腺学会から強く改訂を求めているそうです。
-
抗甲状腺薬とサイロキシン併用療法
第1に、抗甲状腺薬での治療開始すぐに甲状腺機能が低下するような症例では、抗甲状腺薬を減量しても、甲状腺機能低下症の程度が強い場合には、LT4 50μg/日を併用すると甲状腺機能をコントロールしやすい。
第2に、T3優位型バセドウ病では、十分な量の抗甲状腺薬投与しながらLT 4を併用することで、良好な甲状腺機能の維持を目指す。しかし、T3優位型バセドウ病は難治性であるため、131I内用療法や手術を検討すべきである。
第3に131I内用療法後の甲状腺機能低下症はバセドウ眼症のリスクとなるため、LT4を投与することで増悪を阻止できる可能性がある。
第4に活動性の眼症を有する患者では、TSH上昇による眼症増悪を防ぐためにLT 4併用が行われる。その他大量の抗甲状腺薬(MMI 30〜60mg/日を投与して、甲状腺機能低下予防を目的でのLT4併用療法は、寛解率を高める目的としては意味がないとしている。
3)甲状腺中毒症と治療
バセドウ病には、甲状腺中毒症状伴うことが多いが、症状としては体重減少、動悸、心悸亢進、多汗、掻痒感、精神症状、消化器症状、手指振戦、筋力低下、周期性四肢麻痺などがある。これらの症状に対しては、β遮断薬を使用し、妊娠の場合には、可能な限り短期的な使用とし、メトプロロール(セロケン)、プロプラノロール(インデラル)もしくはラベタロールのいずれかを使用することを推奨している。
減量・中止と経過観察の方法
抗甲状腺薬開始後は、重症度に応じて2〜6週間隔で甲状腺機能を確認し、甲状腺機能が十分正常範囲に入ったら、4〜6週間隔でチェックを行い、抗甲状腺薬を漸減していく。
MMI投与量が5mg/日・隔日(2.5mg/日でも可)あるいはPTU50mg/日・隔日投与で、6ヶ月以上甲状腺機能が正常な場合には、休薬を検討しても良い。
最小量維持期間が6ヶ月以上の場合、TRAb陰性・陽性で寛解率に差はないため、このような場合は、陰性化を待って休薬する必要はないとしている。
本ガイドライン発行後の2021年2月に、MMI2.5mg錠が上梓され使用可能となった。MMI5mg/日隔日投与とMMI2.5mg/日・連日投与が同等であるかは明らかになっておらず今後の課題である。
KIを併用した場合の減量方法については触れられていない。KIは抗甲状腺薬よりも効果発現が早いが、減量や中止可能な時期や状態、順序等については今後の検討を要する。
抗甲状腺薬中止後の再発は、1年以内に起こることが多いため、甲状腺機能に2―3ヶ月おきに検査し、1年以降は6〜12ヶ月おきに検査する。1年以上甲状腺機能正常であっても、再発や甲状腺機能低下症の可能性があるため、1年に1回甲状腺機能検査を行う。
参考文献>吉野聡 他, 日内会誌 111:2279-2284, 2022