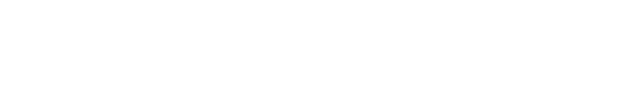25.07.20 ヨウ素摂取が橋本病に及ぼす影響、軽いヨウ素制限について
ポイント>
- 橋本病ではヨウ素過剰摂取にて甲状腺機能が低下する可能性があり、ヨウ素制限で甲状腺機能は改善することがある。
- 橋本病での食事中ヨウ素制限は、和食の摂取に影響が出るほど、厳密になりすぎる必要はない。
日本人のヨウ素摂取量
海に囲まれたわが国は、全国的にヨウ素摂取量が必要量を大幅に上回っている。
独立行政法人 国立・健康栄養研究所によると18歳以上の男女のヨウ素の食事摂取推奨量は130μg/日(=0.13mg 厚労省で示されている上限は3mg=3000μg)であるが、 日本人の食事摂取基準2020年版によると、日本人の食事からのヨウ素摂取量は1から3mg/日と摂取量を大幅にオーバーしていると推定されている。
食事中のヨウ素含有量
一食あたりのヨウ素(μg)は、刻み昆布で18,400、昆布だし(煮出し)で16,500、昆布だし(水出し)、7,950、ひじき(ステンレス釜ゆで)576、ところてん240、めかぶ117、焼き海苔63、カットわかめ50、なまいもこんにゃく47である。
動物性食品では、シメサバ301、まだら(生)280、アワビ(生)120、塩サバ77、うなぎ(蒲焼)62、たらこ(生)52、鶏卵 卵黄(ゆで)40、かき(生)40、普通牛乳32。
以下は、放射性ヨウ素内用療法する方、ヨウ素の取り込み検査等の方がヨウ素制限する際に使用する説明資料です(普通の橋本病の方は制限する必要はありません。主治医に指示されてなければ不要)。
いか、たこ、鮭、えび、帆立貝は、適量であれば食べていいそうです(ヨウ素含有量が少ないため)。
(筆者作成)
そのため、不足となるのは稀であるが、過剰摂取によって潜在性甲状腺機能低下症を引き起こすことがある。
その際、海藻類の摂取を控えるなどの軽いヨウ素制限を行い、3ヶ月後に再度甲状腺ホルモンを再検査する。
橋本病とヨウ素摂取
ヨウ素過剰地域での橋本病の発症頻度についての検討では、ヨウ素過剰摂取地域では、橋本病の発症頻度、潜在性甲状腺機能低下症の発症頻度ともに、ヨウ素欠乏地域より高頻度であった。これらの一部は回復する可能性が示されており、前例が持続するものでは無いようである。ヨウ素が橋本病を誘発するメカニズムとしては、まだはっきり特定されてないが、動物実験において示されているものがある。
診療の実際
初診時にTSHが上昇している患者が受診した場合(橋本病に限らず)、
TSHが10〜20μIU/mL以下→ヨウ素の制限を勧めて、1〜2ヶ月後に再検査を行う。再検査では、TSHが10以上であれば甲状腺ホルモン製剤による補充の適応と考えられる。
注意を要するのが産婦人科を並診している患者である。
不妊症などで子宮卵管造影を施行する場合、油性ヨウ素を含有した製剤を使用するため、数ヶ月にわたって体内に残留することで軽度の甲状腺機能低下をきたすことがある。
また、女性ホルモン製剤の投与を受けている患者では、甲状腺ホルモンの代謝が亢進し、軽度の甲状腺機能低下をきたす可能性がある。これらのケースでは、基本的に産婦人科治療の必要性を重視して必要があれば、甲状腺ホルモン製剤の補充を行う。
また、日常の食事については海藻を全く摂取しないようにしている患者が稀にいらっしゃいます。
もし厳密にヨウ素制限をかけると和食の摂取は困難になり、特に中高年以上の患者では食事選択の幅を著しく狭めてしまうため、ヨウ素の取り込み検査などの特殊な状態を除いて、過度のヨウ素制限は避けた方が良い。
参考文献>
上記
向笠浩司 他,伊藤公一監修, 実地医家のための甲状腺疾患診療の手引き-伊藤病院・大須診療所式 124-127, 2013